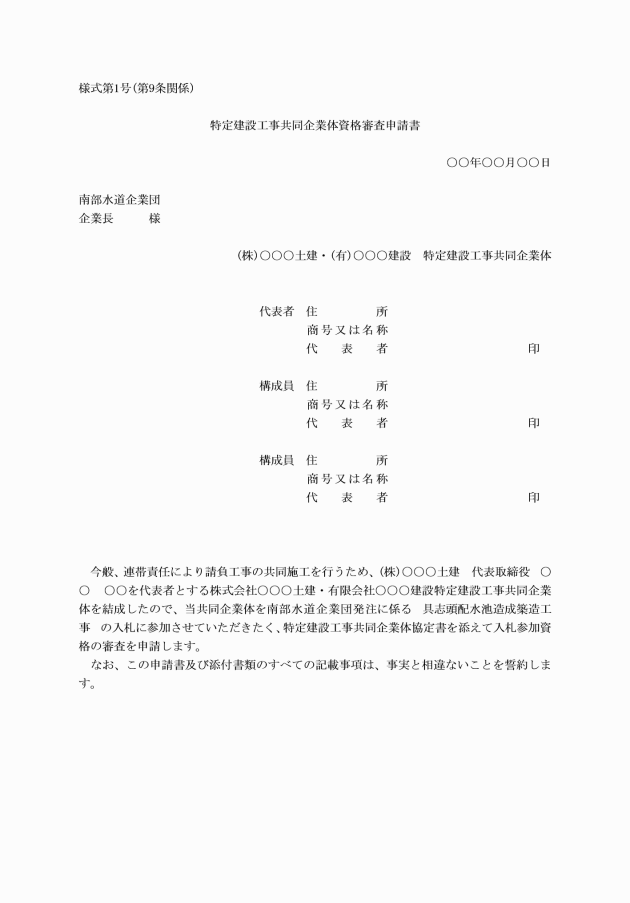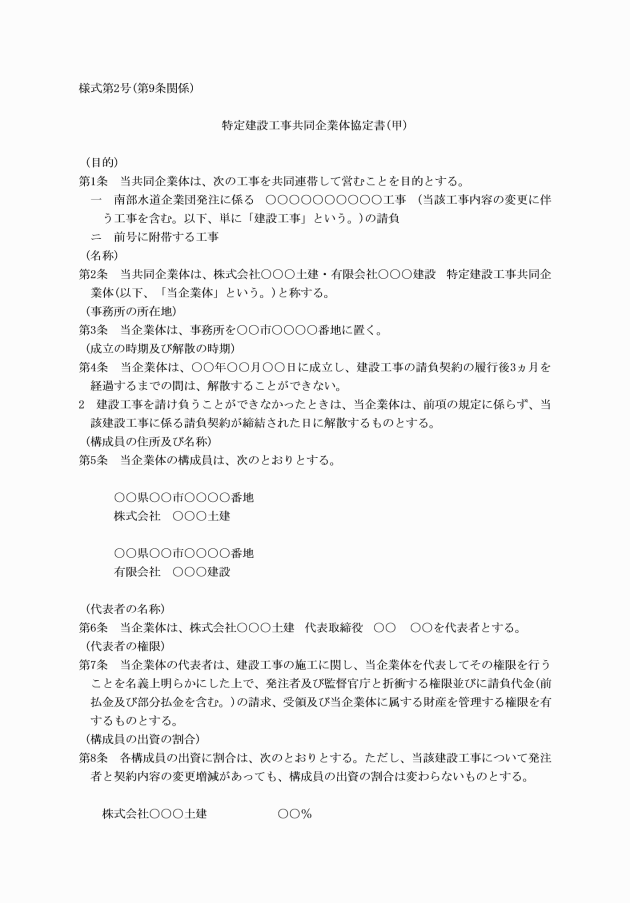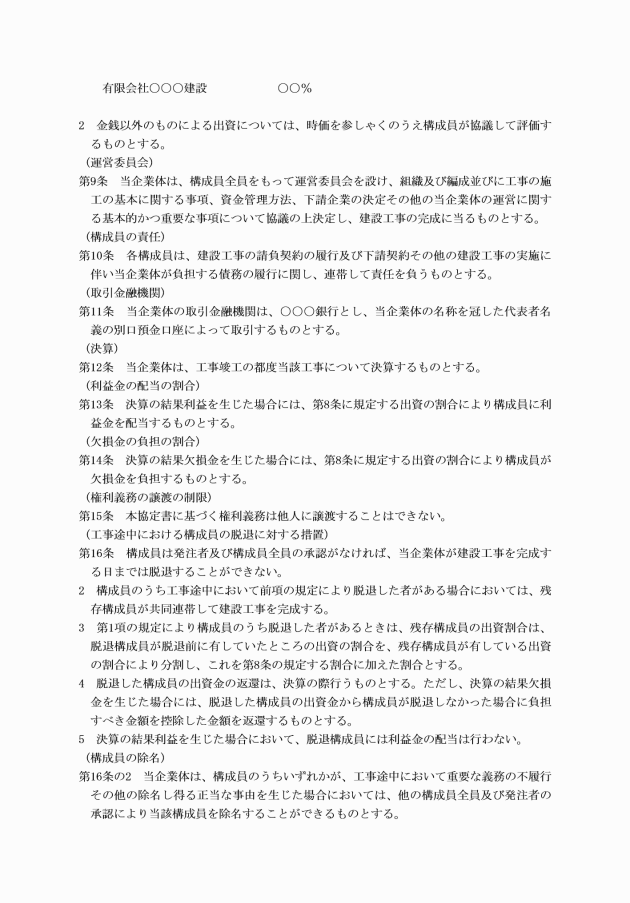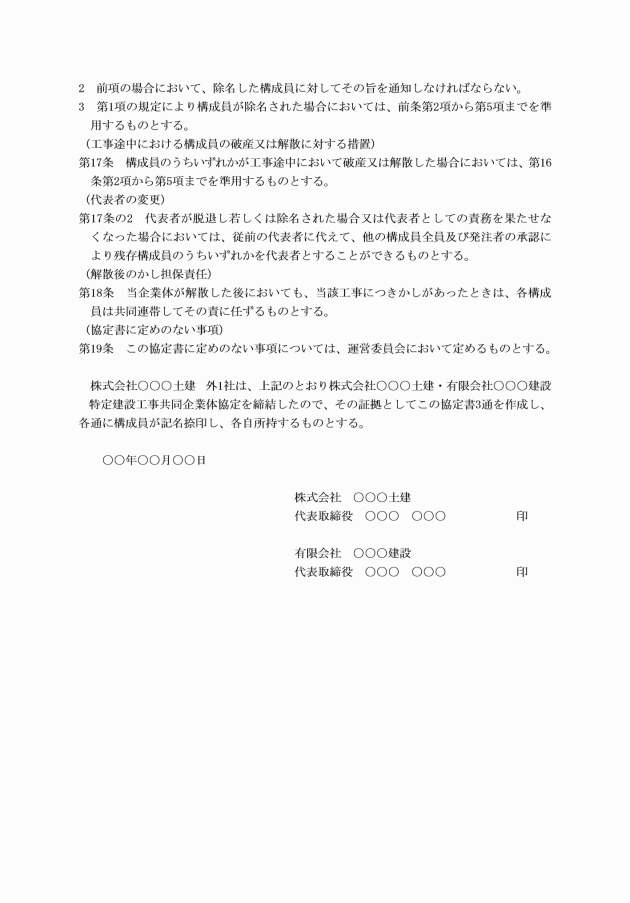○南部水道企業団特定建設工事共同企業体取扱要領
平成22年7月28日
要領第5号
(趣旨)
第1条 この要領は、南部水道企業団(以下「企業団」という。)が発注する建設工事(以下「工事」という。)に係る特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)の施工方式、対象工事等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定JV 企業団が発注する特定の建設工事の施工を目的として結成され、当該工事の完了、引渡しにより解散する共同企業体をいう。
(2) 構成員 工事に係る競争入札参加者の資格を有する建設業者であって、特定JVを構成するものをいう。
(3) 契約担当者 企業長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。
(施工方式)
第3条 特定JVの施工方式は、各構成員が対等の立場で、一体となって施工する共同施工方式(甲)とする。
第4条 契約担当者が特定JVに発注できる工事は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、土木一式工事のうち地盤改良工事、機械器具設置工事及び造園工事等については、この限りでない。
(1) 大規模かつ技術的難度の高い工事
(2) 当該工事の性格等に照らし特定JVによる施工が必要と認められる土木一式工事又は建築一式工事、管工事及び電気工事であって、それぞれ設計額がおおむね次の額以上とする。
ア 土木一式工事 8,000万円
イ 建築一式工事 8,000万円
ウ 管工事 5,000万円
エ 電気工事 5,000万円
(構成員)
第5条 構成員の数は2又は3業者とし、等級格付がなされている業種にあっては、最上位等級に属する者のみ又は最上位等級に属する者と直近下位2等級までの者との組合せとする。
2 構成員は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。ただし、県内企業の育成、公正な競争の促進及び適正な施工の確保を図るため、特に必要があると認められる場合は、この限りでない。
(1) 当該工事に対応する許可業種につき、許可を有しての営業年数が3年以上あること。
(2) 工事規模にかかわらず当該工事を構成する一部の工種を含む工事について元請として一定の実績があり、かつ、当該工事と同種の工事を施工した経験があること。
(3) 全ての構成員が、当該工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置し得ること。
(結成方法)
第6条 特定JVの結成方法は、自主結成とする。
(代表者)
第7条 特定JVの代表者は、構成員のうち最大の施工能力を有する者でなければならないものとする。
(出資比率)
第8条 代表者の出資比率は、構成員のうち最大の出資比率でなければならない。
2 構成員のうち、最小の出資者の出資比率は、次の割合以上でなければならない。
(1) 2業者の場合 30パーセント
(2) 3業者の場合 20パーセント
(1) 特定建設工事共同企業体による工事である旨及び当該工事名
(2) 工事箇所
(3) 工事概要
(4) 特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書の受付期間及び受付場所
(5) 特定JVの構成員の数、組合せ、出資比率、代表者及び構成員の技術的要件等
(6) その他必要と認められる事項
(資格審査等)
第10条 契約担当者は、前条の規定により申請のあった特定建設工事共同企業体入札参加資格審査については、南部水道企業団建設工事請負者指名審査会に諮り、決定するものとする。
(入札参加業者に事故があった場合の取扱い)
第11条 前条の規定に基づき決定された業者に指名停止、倒産等事故があった場合は、当該構成員の属する特定JVは入札に参加する資格を失う。
第12条 前条の規定にかかわらず、構成員の一部について会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされた場合、入札の時から前であれば、残余の構成員が被申立会社に代わる構成員を補充して、新たに特定JVを結成し、確認することができた者については、入札に参加することを認める。この場合において、構成員の一部について破産宣告がなされた場合も同様に取り扱うものとする。
(特定JVの存続期間)
第13条 工事に係る請負契約の相手方となった特定JVの存続期間は、当該工事の完成後3箇月を経過した日までとする。ただし、当該期間満了後においても、当該工事について瑕疵担保責任がある場合は、各構成員は連帯してその責めを負うものとする。
2 当該工事につき結成された特定JVのうち請負契約の相手方とならなかったものは、当該工事に係る請負契約が締結された日をもって解散されたものとみなす。
(要領に定めのない事項)
第14条 この要領に定めのない事項については、別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要領第1号)
この要領は、令和6年4月1日から施行する。